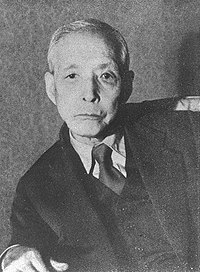2015年12月28日月曜日
2015年12月24日木曜日
杉浦醫院四方山話―461 『アジアの獣医学生』
麻布獣医大学と科学技術振興機構が毎年行っている研究交流事業「さくらサイエンスプラン」は、アジア各国の獣医師と獣医学生が、麻布大学を拠点に研修を積む事業ですが、見学研修会も組み込まれていて、昨年に続き今年も杉浦醫院が見学場所に選定されました。
日本では終息した日本住血吸虫症ですが、中国からフィリッピンまでアジア各国では、未だ蔓延していて、人間から哺乳動物まで罹患していますから、日本住血吸虫症を克服した日本の取り組みについての研修は、参加者には大きな興味とテーマだと教授から説明がありました。
そうは云っても、大学でみっちり講義を受けての見学会ですから、この機会に日本の家屋や民具・農具を観ていただくのも意味あるように思い、提案しましたら「いいですね。日本文化と日本住血吸虫症の二つで」と教授は予定時間も気にせず「両方お願いします」となり、先ずは母屋、納屋、土蔵等の「日本文化」の案内からスタートしました。
矢張り、明治25年建築の母屋は見応えがあるようでした。
 |
専門が獣医ですから、マルヤマ器械店から寄贈された一昔前の日本の医療器具は、母国ではまだ使われているそうです。マルヤマ器械店が閉店する際、「ベトナムの国立病院に一括して寄贈した」と話してくれた丸山太一氏を思い出しました。 |
 |
2階座学スペースに移ってからは、「日本住血吸虫」終息と動物の係りについて、「罹患した動物はどうなったのか?」「人間と同じスチブナールを投与して治療した」「治らなかった動物は?」「残念ですが処分されたようです」と云った具合に質疑応答による研修会をしました。予定時間をはるかに超えても質問が次々で、真剣に学ぶ意欲が熱になり寒さも吹き飛びました。 |
今回の見学会で、 一番予想外だったのは、井戸端の柿の木に多くの留学生が興味深々で、写真を撮りに集まったことでした。中国以外の南アジアの方々でしたが、カキがいい色に実っていたタイミングも良かったのでしょう。
中国か日本が原産と言われている柿は、二日酔いにも効くと云うので好物ですが、日本で多くの品種が生まれ、ヨーロッパやアメリカには日本から伝わり、学名も「Diospyros kaki(ディオスピーロス カキ)」と、「Kaki」がそのまま使われていますから日本を代表する果物であることは確かですが、初めて柿を見た留学生には思いがけない収穫だったのでしょう。
「どんな味なのか?」食べてみたくなるのは万国共通でしょう、皮をむいて切ってあげるとうれしそうに食べながら感想を言い合っていましたから、今日の見学会の一番の思い出であり成果は初体験の「柿」だったかもしれません。
2015年12月16日水曜日
杉浦醫院四方山話―460 『水の上にできた町の出土品』
現在、中央公民館で「昭和町歴史講座」が進行中ですが、前回の教室「かすみ堤」の中で、講師から河西地区のかすみ堤での発掘調査で出土した「うし」は、現在、杉浦醫院に展示してある旨紹介されました。
うしは牛ですから「川に牛?」と疑問符が付きますが、「うし」は川の流れから、堤防を守るために丸太の杭を三角錐や方錐状に組んで作られた水除(みずよけ)です。
 |
| 笛吹市川中島の笛吹川河川敷に設置されている「聖牛」 |
現在でも、笛吹川の石和流域で、コンクリート製の「うし」が連続して建っているのを見ることができますが、信玄堤からの「かすみ堤」の「うし」は、「聖牛(せいぎゅう)」と呼ばれ、武田信玄が考え出したものとされ、写真のように1本の長い杭を斜めに支えるような独特な形に組み上げてあります。
まあ、山梨では信玄堤に始まって信玄餅まで、さかのぼると全て武田信玄に結びつく感もしますから「聖牛」も信玄が編み出したのかどうか?どなたかその根拠をお知りの方はご教示ください。
当館の土蔵横にある旧自動車車庫の建物は、「水の町・昭和」を観ていただく展示会場です。
文化財出土品と云えば「縄文土器」とか「弥生式土器」が一般的ですが、『水の上にできた町・昭和町』ならではの出土品が「うし」ですから、ご覧のように展示してあります。
町内4校の校章には、全てかつて国の天然記念物に指定されていた「ホタル」が描かれているのも「水の上の町」の特徴でしょう。
そのパネルの下と横に展示してあるのが「うし」の杭と解説です。「何だ、ただの丸太棒じゃねーの」と云った声が聞こえて来そうですが、その通り丸太ですが、水に浸かっていた部分は腐食したりしている古丸太です。
この丸太が、何時頃のモノか?考古学の専門機関で精密検査を受ければ確定できるようですが、経費もかかることから、ソコまで特定はしてないのが実態ですが、かすみ堤の発掘調査により、土の中から出てきた遺物ですから、水の町・昭和の貴重な文化財です。
また、豊富な井戸水も昭和の誇りですが、「釣瓶(つるべ)」など井戸に必要な様々な付属品も現代では、文化財です。
それは、「秋の日は急速に日が暮れる」ことを形容して「秋の日は釣瓶落とし」と云った諺にもなっていますが、「釣瓶」がどんなモノか分からなければ、諺も理解できないのが現代でしょう。
「釣瓶」は、元々は井戸水をくみ上げる綱や棒の先に付いていた「桶(おけ)」の事でしたから、井戸の中におろす釣瓶は、井戸を滑り落ちるようにあっという間ですから、秋の日は井戸の釣瓶のように一気暮れるという意味合いでしょう。
しかし、釣瓶は落とすのは簡単ですが、水が入った釣瓶を引き上げるのは大変でしたから、井戸の上に滑車を取り付け、綱には2個の釣瓶が付き、引き上げる動作から引き下げて水が汲めるようになり、「釣瓶」と云えば「滑車」の部分を思い浮かべる人も多くなりました。
そんな訳で、杉浦家の井戸で使っていた「滑車」も展示してありますが、この「滑車」も時代や金額でいろいろな種類があったようですが、手押しポンプからモーターへと井戸水がより便利に汲み上げられるようになって、多くの釣瓶や滑車が廃棄されてしまいました。
「未だ倉庫にある」と云う方は、手押しポンプも含めて当館にご寄贈いただけると「文化財」として後世に残りますので、ご協力ください。
2015年12月14日月曜日
杉浦醫院四方山話―459 『水の上にできたまち【昭和町】』
郷土学習教材「ふるさと山梨」は、 山梨県教育委員会義務教育課が刊行していますが、児童生徒の郷土研究を奨励し、毎年「ふるさと山梨郷土学習コンクール」も開催しています。
当館にも取材に来て表題の「水の上にできたまち【昭和町】」にまとめた西条小学校3年の尾上遥さんが、「第8回ふるさと山梨郷土学習コンクール」小学校の部で優秀賞に輝きました。
受賞した研究発表文を当館にも持参くださいましたが、「昭和町誌」や「昭和町の民話」から昭和47年と平成26年の「住宅地図」などの文献資料と町内在住の何人もの方々に取材して、まとめてあり「優秀賞」にふさわしい内容と構成に、小学3年生当時の我が身を「雲泥の差」という言葉と共に思い起こしてしまいました。
当、「杉浦醫院」は日本住血吸虫症の原因究明と治療法確立に貢献して、多くの患者を救ってきた杉浦健造・三郎父子を昭和町の郷土の偉人として顕彰していく資料館ですが、合わせて町の「郷土資料館」として機能させていこうと「昭和町風土伝承館」と云う接頭語が付いています。
今回の尾上さんの郷土研究「水の上にできたまち【昭和町】」は、ズバリ当館のコンセプトです。
「釜無川の氾濫の歴史」「信玄堤からのかすみ堤」「ミヤイリガイが好んだ湿地帯【よしま】」「天然記念物の源氏ホタル」「ぶっこみ井戸」「甲府市民の水道源・昭和浄水場」「地方病」等々、昭和町の歴史や風土形成は「水の町・昭和」に集約されます。これを調べて、もっとファンタスティックに「水の上に出来た町・昭和町」と表現した尾上さんの感受性には脱帽です。
当館のある西条新田地区の「人口の変化」も200年前・30年前・現在の三段階で調べ、それぞれ129人・548人・1443人と飛躍的に増えたことと新旧の住宅地図で「土地利用の変化」も調べ、「昔はカイコを飼っていたから、桑畑()が多かったけど、今の地図には1つもない」と指摘して、下記の桑畑地図記号を( )内に正確に表示してあります。
このように学習していく中で尾上さんは、田んぼや畑の地図記号と共に新たな記号の解読も必要になり、この記号は桑畑であることを新たな知識として獲得したのでしょう。小学3年生にして「知のヨロビ」を体験することで、研究内容もより正確で、より深くなって行ったのでしょう。
| 国土地理院は一般の畑と区別して桑畑は桑の木を横から見た形を記号表示しています。 |
最後の「まとめとかんそう」では、
「今の昭和町は、昔の釜無川の氾濫で、大きな木が少ないそうです。昭和町は地下に水が豊富な「水の上の町」なので、木を植えれば木も育ちやすくて、緑豊かな町になるから、そうしたらいいと思いました。」と、議員顔負けの提言もより具体的です。
2階座学スペースのテーブル机上に展示してありますので、手に取って詳細をご覧ください。
2015年12月11日金曜日
杉浦醫院四方山話―458 『盲学校の小学生』
過日、県立盲学校小学部の4年生が担任の先生と来館されました。事前にN先生が数回打ち合わせに見えましたが、「バリアフリー」と云った言葉も概念も無かった昭和4年の建築ですから、玄関の段差をはじめ館内はある意味二人には「危険がいっぱい」で、さっそくR君からも「バリアフリーじゃないですね」と指摘されてしまいました。
N先生から「県立博物館や美術館などは、展示品がガラスケースに納まっていて、この子たちには向かないんです。その点ここは、触ったり使ったりが出来るので・・・」と当館を見学場所に設定した理由は聞いていましたので、出来るだけ時間をとって心行くまで体感してもらう様案内しました。
2枚目の写真のようにR君は、「この高さなら踏み台なしで僕は上がれるよ」とベッドにも自力で上がりましたから、「地方病の患者さんはここに寝て、三郎先生が静脈注射を打って、お腹の門脈に住んでいた虫を退治してもらいました」と、具体的に話すことも出来ました。
農具や石碑からピアノまで杉浦醫院内にある全てを2時間かけて体感しましたが、DVDも観賞して「健造先生と三郎先生の声を聴きたかった」と開口一番の感想に映像を音声で想像する二人には、健造先生と三郎先生の声が頼りだったことを教えられました。
 |
| 一つ一つ自分の手や体で確認して、見学した物の形や名前を覚えていく好奇心と意欲に案内し甲斐がありました |
2015年11月27日金曜日
杉浦醫院四方山話―457 『杉浦もみじ伝承の会』
11月23日付け山日新聞社会面「中央道」欄でも≪モミジの紅葉が映える庭園で「和」に染まった時間を満喫≫と、報道されましたが、22日(日)に2回目となる「杉浦もみじ伝承の会」を開催しました。
町は、「第5次総合計画」で新しいまちづくりの目標を掲げ、その理念を
とし、まちづくりの基本目標(テーマ)を
と、町の意思を表現しています。
今回の「杉浦もみじ伝承の会」も『ともに創る』『協働』の具体的実践として、「和」のネットワーク化を進める民間団体「マイパラ」と協働して取り組むことにより、『うるおいと躍動の都市 昭和』に寄与しようと云う趣旨を秘めつつ、多くの町民が杉浦醫院庭園で楽しい時間を共有出来たらと開催しました。
昨年の500人を大きく上回る800人の方々に「モミジの紅葉が映える庭園で「和」に染まった時間を満喫」していただきましたので、その模様を写真にて紹介いたします。
 |
| 幕開けは「手品」の独演会。種も仕掛けもある高度な手品を参加者は見入っていました。 |
 |
| 庭園内の表も裏も「和」の店舗26軒が軒を連ねました。 |
 |
| 出店者も来館者も和装の方々も多く、雰囲気を醸していました。 |
 |
| 手づくりの籠には、外国人の興味も・・・ |
 |
| もみじや庭園での撮影会を企画した写真展 |

午後の舞台は身延山高校「雅楽部」の演奏
杉浦醫院母屋の舞台にピッタリ!!
2015年11月18日水曜日
杉浦醫院四方山話―456 『杉浦醫院のピアノと過ごす午後のコンサート』
11月1日(日)に当館で「杉浦醫院のピアノと過ごす午後のコンサート」が開催されました。
折に触れて杉浦醫院のピアノは紹介してきましたが、「皇太子(現天皇)生誕記念」とか「日本に数台」と云った価値もさることながら、矢張りピアノは「弾いて」「弾かれて」その音色や響きを実際に聴いた人の評価で価値が決まることを実感しました。
今回の院内コンサートは、出演者お二人の総意で「杉浦醫院のピアノと過ごす午後のコンサート」と銘打たれました。
当日のプログラムも杉浦誠さんにご用意いただきましたが、全16曲の曲目と作曲家のエピソードなども演奏の合間にお二人から紹介され、曲目選定も音楽史の概要に沿ったものでした。
好評と云えば、ピアノの音色が「昨年と全く違う」と参加者からも指摘されましたが、ピアニストの佐藤恵美さんもスピーチの中で、「素晴らしい音で、弾いていて楽しくなります」とか「このピアノが欲しくなってしまいました」と話され、杉浦誠さんも「流石、辻村さんですね。とてもいい音色で聴き入ってしまいますね」と蘇ったピアノに感嘆の声が続きました。
圧巻は杉浦誠氏のテノールで、マイクを使わなくても駐車場まで届く声量は、体全体から声を出しているようにも見え、院内を揺るがす程の迫力で、「声楽家の歌唱をこんなに近くで目の当たりに出来たのは初めてで感激しました」と参加者も興奮気味でした。
昨年の院内コンサートでは、数曲で退席した純子さんも「私は視力が衰えて、見えませんから廊下で聴かせていただきます」と条件の悪い廊下でしたが、自分が使ったピアノの音色を懐かしみながら最後まで聴き通しました。
休憩時間に純子さんにこのピアノにまつわる思い出などインタビューしましたが、「こんなにいい演奏会を開いていただいて、ピアノも新館もとても喜んでいると思います」と話すと、会場は拍手に包まれ、文字どおり「杉浦醫院のピアノと過ごす」時間が共有出来たことを喜び合いました。
コンサート会場のような音響条件は望むべくもない院内コンサートですが、観客席はガラス戸を外した診察室ですから、ピアノ再生にご尽力いただいた辻村氏が、「客席が向こうならピアノの位置はここしかありません」と蘇ったピアノを4人で押して、東側の窓際に移動しました。
「客席に向かって反響版を上げないとせっかくの音がお客さんに届きません。グランドピアノがあっても反対向きのまま使われている学校などよくありますが、もったいないです」と、これまでの位置から演奏に使うことを前提にした場所に移動したのも好評だった一因かもしれません。
ご出演下さいました杉浦誠様と佐藤恵美様には重ねてお礼申し上げます。
2015年11月16日月曜日
杉浦醫院四方山話―455 『菊香る玄関』
11月1日の院内コンサートに向けて前五話で、ボランティアでピアノ再生に取り組んでいただいた富士市の辻村音楽企画店のお二人を紹介させていただきましたが、毎年季節ごと育てた花で玄関を飾っていただいてきた西条一区の堀之内一郎さんが、コンサートの開催に合わせるかのように数日前にご覧の菊を玄関前に設置してくださいました。
これも毎回のことですが、私たちに気付かれないように休館日に置いて行くと云う奥ゆかしさも花を育てる人には自然に備わる美意識なのでしょうか。
つくづく、杉浦醫院は控え目でボランティア精神に富んだ心ある方々に支えられていることを実感し、感謝いたします。
今年の堀之内さんの菊作品をご紹介します。
背も一番高く3つの大輪の花が豪華なこの菊は「黄糸太」です。
これは、芽の先を摘心して、一本の苗から3本の側枝を伸ばし支柱で支え、一枝に一輪花を付けるよう仕立ててあります。
3本の中で一番高い枝が「天」で真ん中後ろに、残り2本が「地」「人」で、背の高さを「天」「地」「人」の順になるよう造られています。これを「三段仕立て盆養」と云うそうです。
この菊名は「うすぼたん」です。
このように花を丸く咲かす造り方を「ダルマづくり」と呼ぶそうです。これも「3本仕立て」で、「天」の高さを65センチ以下に収めるのが条件だそうで、植物の成長を抑制する矮化剤(わいかざい)を使ってこの条件に合うように造るのだそうです。
和菊の代表でもある「元禄丸」です。
上からの撮影で分かりにくいのですが、花は真ん中が高くなるように咲いています。
このように大菊、中菊、小菊を左右に3鉢置くと、この3鉢もそれぞれ「天」「地」「人」の順になっていますから、堀之内さんはそこまで計算して育てて設置してくれていることが分かります。
また、鉢には、それぞれの菊の名前が書かれた小さな名札まで付けてくれますから、何も知らない私でも菊の名前も教えていただき、訳知り顔で紹介することもできました。
更に、左右3鉢の足元があらわにならない様に丸菊をそれぞれ2鉢ずつ配してと、細かなところまで気配りが行き届いていることにあらためて感謝申し上げます。
2015年11月12日木曜日
杉浦醫院四方山話―454 『 ピアノ再生物語5-整音作業』
辻村氏と臼間氏の作業工程を実見し、説明を受ける中で分かったことは、辻村氏が実践しているピアノのメンテナンスは、先ず埃や錆び、汚れを徹底的に綺麗にして、アクション各部を主にドライバーで調整する「整調」作業をし、次に音律を正す「調律」を施すと云う工程です。
ですから、一般的な「ピアノの調律」は、「整調」もこの後施した「整音」も入っていないので、一人でも1~2時間で終わることが出来ることも分かりました。
「磨き」「整調」「調律」が完了した時点で、既に6時間が経過しましたが、辻村氏は「後は整音だけですから」と云うので、5時過ぎには終わるものと勝手に思いましたが・・・・
「整音」作業は、正確なことは分かりませんが、ピアノのハンマー1本1本のフェルトの硬さを調整する作業のようで、これによっていわゆる「ピアノの音色」が決まるようです。
始まった「整音」作業は、先ずハンマーのフェルトにある「硬度分布」にそって、そこに針で穴をあけて調整するという細かい作業でした。
ハンマーのどの位置に幾つ針を入れるかは決まっていないので、二人の経験から編み出されるカンなのでしょうか?
このハンマーに針を刺す作業で「整音」が終わるものと思っていましたら、今度は、ご覧のようにヤスリでハンマーのフェルトの形を整えるかのような作業が始まりました。この作業がどう音色づくりに係るのかは聞き漏らしてしまいお伝えできませんが、針刺し同様これも一本一本の手作業ですから、この時点で6時30分を過ぎていました。
その頃、午前中、取材した山梨放送が夕方のワイドニュースで、二人の修復作の様子を放映したのでしょう、町長から電話が入りました.
「最後の工程のようですが、まだ作業が続いています」と応えると「それじゃあ、直ぐ挨拶に行くから」と、消防団団長で鍛え上げた町長の即断力に「さすが」と感心し、ボランティアでここまでしていただいているお二人に町長からの挨拶は何よりのお礼になるので、感謝しつつお願いしました。
作業終了間際に丁度、町長が駆けつけてくれましたので、完成したピアノを前に記念撮影も出来ましたが、お二人は休む間もなく工具の片づけや車への積み込みにかかり、7時30分には「真っ直ぐ帰りますから」と帰途につかれました。
お二人を見送りながら思わず浮かんだのは「疾風のように現われて、疾風のように去って行く、月光仮面のおじさんは、正義の味方よ良い人よ」のフレーズで、辻村氏と臼間氏の仕事ぶりと人としての実存は、私には、さながら現代に蘇った「月光仮面」そのもでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5回に渡り、今回の当館ピアノ再生作業について、ご紹介してきましたが、ピアノ素人の視点からの記述で、内容的に辻村氏の本意あるいは説明と違う、不正確な部分もあるかと思います。お気づきの点がありましたら、電話にてご教示いただけたら幸いです。055-275-1400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年11月11日水曜日
杉浦醫院四方山話―453 『 ピアノ再生物語4-調律師資格』
今回、「一日で仕上げます」には、社長の辻村氏と主任技術者の臼間氏の二人での作業が前提だったようで、指示や注意などの言葉は一切なく、息の合った分担作業が続きました。
例えば鍵盤関係では、1本1本磨いたり、締めたり、削ったりの作業ですから、黒鍵36、白鍵52の合計88鍵の鍵盤を二人で左右から始めることで半分の時間で出来ることが分かりました.仕事の手を休めることなくテレビや新聞の取材の方々に説明したり、質問にも気安く応じていただきました
 |
| こう云う貴重なピアノに係れ胸がときめく程やりがいがあります」と若々しくインタビューに答える辻村氏 |
「調律師になるのには何処で学ぶんですか?」
「ヤマハやカワイには、調律師養成学校もありますが、国立音大など音大や専門 学校にもあります。静岡には楽器メーカーが多いので調律師も多いんじゃないですか。学校出たから出来ると云うモノじゃないですがね」
「臼間さんもカワイ出身ですか?」
「私は彫金をしていたんですが、辻村さんの仕事を観て、彫金と同じような手作業で大きなピアノを蘇らせていくのに感動したんです]
「二人のお嬢さんは、上智と東大ですから頭は良いのは分かっていましたが、兎に角呑み込みが早い。それにやる気があるから、私に就いて修業して今ではウチの柱です」と、臼間氏は辻村氏個人から技術を習得して調律師になったことも知り、二人の「阿吽の呼吸」は、そういう過程で自然に育まれたものでしょう。
内外の磨き作業と整調作業が終わったピアノの底板には、埃で見えなかったエンブレムもご覧のように見事に蘇りました。
「現在のヤマハのエンブレムは角ばった模様の中に字体が違うヤマハの文字だから、いやあ~このエンブレムは初めてです。これだけでも貴重ですね」と辻村氏。
臼間氏も写真に収めていましたが、このようにピアノの内部を上から目の当たりに出来たのも外せるものは全て外しての作業だからこそでした。
2015年11月6日金曜日
杉浦醫院四方山話―452 『 ピアノ再生物語3-整調作業ー』
錆びたチューニングピンとピアノ線を磨くには、ご覧のようなワイヤーの錆び取り工具でゴシゴシ磨くしかないそうで、粉塵が舞う中、根気強い作業が続きました。研磨前と研磨後では、ピンや線に雲泥の差が出て「こんなに綺麗になる」から作業にも力が入るのだそうです。
内部の磨き作業が終わるとピアノは、至る所でドライバーでの調節が出来る仕組みになっていて、一本一本ネジを締めたり緩めたりの手作業が必要になることを知りました。
調整箇所によって大小のドライバーを使い分けての作業が延々と続きましたが「電動工具では締めすぎたり微妙な調整が出来ませんからドライバーでの手作業になりますね」と、ご覧のように辻村氏の手首から湿布は外せないようです。
取り外せないピアノ内部の調整は暗いこともあって、左手にライト、右手に工具での作業ですが、一か所一か所丹念に調整していくのは、鍵盤に指先を落してピアノを弾いたとき、音が出るまでスムーズに同じ早さになるように「整調」する必要からだそうです。良く耳にする「鍵盤によってタッチが違う」と云った事を無くす調整でしょうか。
これを「アクションの整調作業」と呼ぶそうですが、この整調作業はしなくてもピアノの音は出ますし、整調が多少おかしくても素人には分からないそうですが、ピアニストなら直ぐ分かるそうですから、この「整調作業」は一番大切な部分だからこそ時間を掛けるのだそうです。
また、見えないこの調整作業に腕をふるう所に、調律師の醍醐味とやりがいがあるようで、 辻村氏と臼間氏は「これをやらない」調律作業が主流になっていることに警告を発しているかのようでした。
2015年11月5日木曜日
杉浦醫院四方山話―451 『 ピアノ再生物語2-出荷検査』
前話で、辻村氏の「ピアノ調律論」は「出来る限り工場出荷当時の状態に戻すこと」と、紹介しましたが、辻村氏は現在の「辻村音楽企画店」を起業して独立するまで、河合楽器でピアノの製造に従事し、最終の「出荷検査技師」を永く務めていたそうです。
ですから、カワイピアノをお持ちの方は、ピアノの製造番号が付されたお客様カードの一番上にある「出荷検査」の「技師名」をご確認ください。
「技師名に私の名前・辻村晴男とあるカワイピアノが相当数あります」と話し、このピアノの内部に保管されているお客様カードを取り出しました。
「おっ、これは尾島さんだ。この尾島一二と云う人はヤマハの有名な技師で、ピアノの製造に係った人なら知らない人はいません」と感慨深げです。
「杉浦三郎様御所有」と記された桜色のカードには、先ず「御注意」が記載されています。
「弊社製ピアノの調律修繕は生みの親の弊社技師に御任せ願ひます。カードの記録は後々迄仕事の責任を明らかにしてピアノの御保存上重要な役目をするものでありますから必ず記入させて頂きます」
その下に「山葉ピアノ 平型NO.記念 製番NO.21346」とあり、1から12までの表の1出荷検査の技師名に「尾島一二」とあり「尾島印」と「9年7月14日」がしっかり読み取れます。
2納入検査は、「内藤正民」「内藤の角印」に「9年7月20日」とあります。
上記から、昭和8年に皇太子生誕記念として受注生産したこのピアノを三郎先生が甲府の内藤楽器に注文し、約一年後の7月14日に浜松市のヤマハ工場から出荷され、内藤楽器の内藤正民氏が7月20日にこの応接室に納入したことが分かります。
アクションを外し鍵盤を外すと鍵盤の下から内部にかけて積年の埃がたまっていました。
「この埃が虫食いの原因になるんです。」と、虫が食べた跡がアルファッベッドのような模様になっている緑のフェルトを指差し「この程度ならまだ交換の必要はありませんが、計画的に交換していけると一番いいんですがね」と、埃を専用掃除機で取り去ると、ピアノ線の錆び取り作業など内部の磨きを黙々と進めるお二人に、マスクとエプロンは必需品でしたが、肝心な細かい作業になると手袋は外して・・・と、再生に掛ける情熱がひしひしと感じられました。
杉浦醫院四方山話―450 『 ピアノ再生物語1-心意気』
10月28日(水)午前8時に静岡県富士市を70歳になる辻村晴男氏は、愛車のスカイアクティブテクノロジーDデミオに技術主任・臼間雅代氏と必要な工具を積み込み、国道139号を登り、精進湖線を下り、一路杉浦醫院を目指しました。
辻村音楽企画店のピアノ調律部門を担う臼間氏は、出勤前に富士市内にある広見公園に行き、公園内に移築保存されている富士市の指定文化財「杉浦医院」の建物を撮影してからの出勤だったようです。
それは、かつて富士市内にあった杉浦医院を私たち見せてあげようと云う気遣いからでした。
朝陽にまぶしく輝く青を基調にした瀟洒な洋館は、三郎先生の兄・杉浦秀宜氏が西条新田から富士市伝馬町に移り、2代に渡り70年間開院していた「杉浦医院」です。
| 大正8年建築の富士市の杉浦医院 |
超ご多忙の中、ピアニスト佐藤恵美氏とのスケジュール調整などを行い、11月1日の院内コンサート実現にご尽力くださいましたテノール歌手の杉浦誠先生は、「私が杉浦医院を潰しました」と笑いながらおっしゃいますが、心に期すモノがあったのでしょう富士杉浦医院を閉じ、現在は「熱海所記念病院」の医院長を務める外科医です。
この富士杉浦医院で、誠氏の父に家族全員が世話になったと云う辻村氏が、誠先生が祖父の実家の杉浦醫院で院内コンサートを計画していることを知り、「杉浦先生の為ならば」と、ピアノの修復再生を買って出てくれました。
9月にピアノの状態確認の為、4人で当館を訪れ、「これならば、二人で一日かければ見違えるようになります。杉浦先生のコンサートに間に合う様、日にちを調整して来ますから、ボランティアで是非やらせて下さい。」と・・・
10時前に昭和町内に入るとコンビニを見つけた辻村氏は「迷惑をかけないようにおにぎりを買っていこう」とお茶とおにぎりの昼食を用意するなどボランティアに徹底しようと云うこだわりは、矢張り「職人の心意気」からでしょうか。
前後して、YBS山梨放送のスタッフが、まぼろしのピアノ再生修復の模様を記録しようとカメラを備えたところに辻村氏と臼間氏が、道具を持参して来館しました。
休む間もなく「先ずは、内外の磨きから」と、手慣れた要領で、鍵盤と天板を外しにかかりました。
辻村氏の「ピアノ調律論」は、「ピアノが工場から出荷された時の状態に出来る限り戻すこと」と明快ですから、単に音合わせのような「調律」と一線を画した作業が、著名なピアニストからの指名にも繋がっているでしょう。
今回の辻村音楽企画店のボランティア作業を「ピアノ再生物語」として、詳しくご紹介していきます。
2015年10月26日月曜日
杉浦醫院四方山話―449 『大村智博士・甘利山スキー場』
大村博士のノーベル賞受賞決定で、大村氏の現在と過去がマスコミのニュースや特集番組でどんどん公になっていますが、大村氏自らもどんな内容のインタビューにも応えている感じで、飾らない人柄が浮き彫りになり、庶民的な明るい話題を提供し続けているのも「脛に傷」一つ持たない人生を送って来た自信でもあるのでしょう。
その中で、5人兄弟の長男として生まれた大村氏ですが、姉が語った弟の少年期の話で「家畜の世話など農業の手伝いはしたが勉強は全然しないで、ベルトを外してビュンビュン振り回すガキ大将だった」と云った話に親近感を覚えました。
今でこそ、ベルトビュンビュンは見かけなくなりましたが、昭和30年代後半の中学校でもケンカになるとベルトビュンビュンでしたし、高じて腰にベルト以外にクサリも巻いてケンカに備えていたツワモノもいましたから、大村氏はケンカでも負けず嫌いな少年だったのでしょう。
もう一つは、韮崎高校でスキー部主将を務め、国体の山梨県代表として活躍したスポーツマンだったと云うエピソードです。
私より15年近く前の世代で、部活にスキーを選択出来た大村少年は、とても恵まれた家庭に育ったんだと思いました。
それは、昭和40年代になっても高校スポーツで競技スキーをしていたのは、高価なスキー道具や長野県のスキー場に通う交通費や宿泊費等々から、ごく限られた裕福な家庭の子女だったからです。
そんな折、韮崎市出身の高校の同級生Y君が、大村博士の少年時代を自分の少年時代と重ねた感想をメールリンクに載せて、韮崎の風土について教えてくれました。
レンゲツツジ咲く現在の甘利山山頂
韮崎市では大村少年のころからY少年の時代位まで、市内の甘利山でスキー大会が開催されていて、その大会目指して、甘利山でスキーの練習をするのが一般的な少年の冬のスポーツであり楽しみでもあったそうです。
当然、リフトなど無かったそうですから滑り降りたらスキー板を担いで登るの連続で、Y君も「あれで足腰が鍛えられた」そうですから、大会で優勝したと云う大村氏ですから誰よりも多く練習に明け暮れたのでしょう。
現在の甘利山は、日本百名山にもなっていますが、自動車が入る道路整備や折々の花が楽しめる植栽等で、登山と云うよりハイキング向けの山と云った感じですが、山頂にあったと云うスキー場まで登る前に市内各所から甘利山までも歩いたり、自転車で行ったのでしょうから、韮崎の昔の少年は皆、健脚揃いだったことでしょう。
人工降雪機の発達で、現在は県内にも複数のスキー場がありますが、「甘利山と雪」はピンと来ません。
しかし、韮崎市史にも「1956年(昭和31年)第一回県下甘利山スキー大会開催」とありますから、大村氏が高校生になった1950年以前から、「韮崎市中高校生甘利山スキー大会」が開催されていたのでしょう。
スキー場が頂上だったのも確実な積雪を確保する必要からだったのでしょうが、数十年に一度の大雪はあっても近年ではスキーが出来る程の積雪は無いでしょうから、矢張り「地球は温暖化」しているのでしょうか?
2015年10月24日土曜日
杉浦醫院四方山話―448 『大村智博士・故郷』
大村智博士がノーベル賞受賞決定後、初めて故郷韮崎市神山町の自宅に帰り、地元の方々から祝福を受けていることを今日もマスコミ各社が大きく報じています。(10月18日)
大村博士は、「韮崎に帰って故郷の自然に包まれ鋭気を養い、東京に戻って研究に取り組む。この繰り返しが今回の受賞に繋がった」と語っているように韮崎と東京を行き来してきた中で、韮崎の自宅を取り囲むように美術館・そば店舗・温泉施設も造り、地元の人々にも喜ばれてきたのでしょう。
韮崎市内は、大村博士の受賞祝賀ムードで活気づいていますが、これまで韮崎市が誇る偉人は、小林一三氏でした。
もう十年位前でしょうか、「小林一三出身の街・韮崎」として、市内の全ての学校に宝塚のシンボル・スミレの花を植樹して、子どもに小林一三の偉業を教え、街をスミレでいっぱいにする「町おこし」を市が始めたと云ったニュースを聞いた記憶があります。
小林一三は、関西を舞台に阪急電鉄や宝塚歌劇団、阪急百貨店、東宝などを次々創業した日本の私鉄経営のモデルを作り上げた実業家として有名ですが、政治家でもありました。
甲府の中心街にあった「甲宝シネマ」は、戦前、小林一三が私財を投じて甲府市太田町に「甲府宝塚劇場」として開館した老舗映画館でしたから、「宝塚劇場がある甲府」も小林一三のプレゼントだったのですが、 若尾逸平や根津嘉一郎のように東京で成功した甲州財閥に比べ、小林一三の名は甲州人には浸透性には欠ける嫌いもあります。
それは、小林氏の誇張された形容でしょうが「故郷に一度も帰らなかった男」から来ているのかも知れません。
同じ韮崎生まれの小林氏と大村氏ですが、故郷・韮崎へのスタンスは180度違っていたようですから、今回の大村氏のような祝賀行事は、生前の小林氏には無かったのだろうと思います。
小林氏が1873年(明治6年)、大村氏は、1935年(昭和10年)と生まれた時代は違いますが、同郷で名を成した二人の故郷へのスタンスの違いは、どこから来たのでしょう?
小林氏は韮崎市中心街の商家の生まれ、大村氏は市内を見おろす農家の生まれの違い?
小林氏は幼くして市外の縁者の家で育ったのに対し、大村氏は大学卒業まで韮崎で農業を手伝いながら成長した成育歴の違い?
小林氏は慶應義塾卒、大村氏は山梨大卒と最終学校の違い?
小林氏は山梨の峡北地区から関西一円へと拡大した商圏での実業世界で、大村氏は化学という学問研究世界でと、思考、活躍の場の違い?
等々が凡人が思い当たる推測ですが、まあ、凡人同士の場合は、「妻」のスタンスの違いが決定的でしたから、あながち偉人にも共通するのかも知れません。
杉浦父子のように外で学んだ後は、故郷で全うした人生、大村氏のように故郷を大切に往復する人生、小林氏のように故郷を振り向かない人生と違いますが、共通して「故郷がホオッテおかない」ところに偉業を為した偉人たるゆえんがあるのでしょう。
2015年10月19日月曜日
杉浦醫院四方山話―447『大村智博士・地方病』
「一億円宝くじに当たると急に親戚が増える」と同じで現象でしょうか、大村智博士のノーベル賞受賞で、当館にも問い合わせが舞い込むようになりました。
それは、受賞決定後の超多忙な博士には取材できないマスコミが、安直な方法として当館に問い合わせてきたのでしょうが、「韮崎の農村生活での成育歴が、学問や研究への基本姿勢を形成した」と云う博士の話が繰り返し報道されていることから、「韮崎にも地方病の患者はいたのか?」と云った問い合わせから「博士が寄生虫病の薬の開発に向かったのは地方病が影響したのか?」と云った、本人に取材してもらわなければ分からないことまで多種です。
そんな訳で、大村智博士の研究と山梨の風土病「地方病」との関係を整理してみるのも無駄ではないでしょうから、客観的な年代に即して推測してみたいと思います。
大村博士の本格的研究生活のスタートを1963年に山梨大学工学部発酵生産学科に文部教官として赴任した年とすると昭和38年からになります。
地方病は、昭和30年代になると住民の感染調査、診断も定期的に行われ、検便による虫卵検査からより正確な皮内反応検査が主流になるなど治療の徹底と予防が浸透し、県内での新規感染者数は激減していった時代と重なります。
特に特徴的な腹水がたまる重症患者は稀になり、昭和40年代になると患者に感染したセルカリア数も少く、便中に虫卵を見つけることも困難になったそうですから、昭和30年代以降は、地方病の流行は終末期を迎えたと云えます。
山梨県による地方病予防宣伝カー。1955年(昭和30年)頃
ですから、大村博士が故郷の風土病・地方病撲滅を念頭に研究を始めたと云うことは無かったのでしょうが、地方病の有病地を名指しで謡った哀歌にも「 中割(なかのわり)に嫁へ行くなら、買ってやるぞや経帷子に棺桶」と謡われた韮崎市中割は、大村博士が育った韮崎市神山地区に隣接していますから、大村博士もこの病に罹った農民を目の当たりにして育ったことは想像に難くありません。
更に、山梨県内では終息に向かったこの病も昭和3、40年代の東南アジアでは、猛威を振るっていましたから、甲府市立病院の林正高先生がフィリッピンの患者救済に起ちあがったように山梨大学から北里大学へと研究拠点も移した大村博士が、世界を視野にアフリカの風土病を研究対象に薬の開発を始めても不思議ではありません。
また、大村博士は現在もブラジルの研究機関と連携して、現地の住血吸虫症患者に有効な薬の研究開発をしているそうですから、一つの国から一つの病を終息させた故郷・山梨の地方病=日本住血吸虫症根絶の取り組みや歴史は、故郷思いの博士の中に脈々と息づいているのでしょう。
2015年10月9日金曜日
杉浦醫院四方山話―446 『大村智博士・科学映像館』
今年のノーベル医学・生理学賞を韮崎市出身の大村智氏が受賞され、山梨県人初のこの快挙を山梨日日新聞は連日大きく伝え、県内は大村フィーバー現象で、県民の士気も上がっているように感じますが、物理学賞も日本人・梶田隆章氏ですから、山梨県に限らず日本全体が元気になっている感もします。
これは、大村博士=日本人=山梨県人=韮崎高校=山梨大学等から、自分は「日本人=山梨県人=韮崎高校=山梨大学と4つもダブってる」とか云って、共通項を競っても何の意味もないのは承知でしょうが、目に余る劣化で発信力も統治力も無きに等しい日本の政治家と政治のテイタラクに厭世気味の日本人には、学問分野での世界的活躍で溜飲を下げたと云うことでしょう。
大村博士と同世代で「カテプシンK」の発見者でもある久米川正好氏は、大村氏同様「世間のお役にたつ仕事」をライフワークに大学退官後は『科学映像館』を主宰している研究者です。
『科学映像館』の映像は、インターネットで「いつでも・どこでも・だれでも」無料で観賞できる画期的な「映画館」ですが、久米川先生からも山梨県人である私に「この度はおめでとうございます」と大村氏の受賞を祝福する電話をいただきましたので、間違いなく山梨県にとって大村氏の受賞は、計り知れない効果をもたらしていることが実感できます。
同時に久米川先生から『科学映像館』の映像の中にも大村智氏の関連映像があることを教えていただきました。
「科学映像館」トップページ左のジャンル検索の「科学映画制作会社検索」にある「ヨネ・プロダクション」をクリックすると「命を守る 北里研究所ー伝統と未来ー」があります。
この映像は、北里研究所が創立80周年を迎えた1990年に「大村智監修」で制作されたもので、ヨネ・プロダクションH・P上の最新YONE Productionの日記でも大村博士のノーベル賞受賞に合わせ、この作品の英語デジタル版化を進めていることを報じています。 この英語版も科学映像館から配信されますので、科学映像館へのアクセスもこれまで以上に国際化することでしょう。
「ノーベル映像賞」があれば、遠からず久米川先生もノミネートでしょうが、貴重な科学映像を中心にこれだけの映像をお一人で収集、配信している業績は、既存のジャンルでは「ノーベル平和賞」でしょうか。
また、久米川先生からの情報では、来週中には大村智関連映像として「愛犬の命を守るために」が、科学映像館から配信されるそうです。
ご存知のように大村博士の開発した「イベルメクチン」は、多くの人間の命を救ってきましたが、犬の肺動脈に寄生するフィラリアが原因で、1980年まで平均寿命が3歳にも届かなかった犬の命も10年近く伸びましたから、大村博士の「イベルメクチン」は、私のミックス犬14歳の命も守ってきた訳で、感謝に堪えず14歳の痴呆犬になり代わり御礼申し上げ、映画 「愛犬の命を守るために」を心待ちに一緒に拝観したいと思います。
2015年10月7日水曜日
杉浦醫院四方山話―445 『放送ライブラリー』
横浜の「日本新聞博物館」は、定期的なPRもあり知っていましたが、同じビル内に「放送ライブラリー」と云う施設のあることを初めて知りました。
ここでは、過去のテレビ、ラジオ番組からCMまで約3万本を無料で公開しているそうですから、「時間だけはある」年金生活者になったら入り浸ってみたい誘惑に駆られます。
ホームページを開いてみると収蔵されている番組やCMも検索出来るようになっていました。早速「サントリーホワイト」と入力すると1971年から1998年までの5本のCMが登録されていて、お目当てのサミー・デイビス・ジュニア出演の「Get with it」と菅原文太出演の「ホワイト 文太・夜桜」もあることが分かり、近々行ってみたくなりました。
それは、「科学映像館」のように観たい映像をインターネットで観れるのではなく、収蔵作品とそのデータを確認して、放送ライブラリー館内で観賞するシステムであることが地方在住者には残念でもありました。
そうは云ってもあのサミー・デイビス・ジュニアの絶妙なアドリブの「Get with it」が1972年の作品、菅原文太の名セリフ「あんたも発展途上人」の「ホワイト 文太・夜桜」が1982年の作品であったことなども確認でき、懐かしいだけでなく現代のCMにない質の高さをじっくり鑑賞したくなりましたから、足を運ぶ価値は十分あるように思います。
余談が長くなりましたが、この放送ライブラリーから「ご出演ラジオ番組の放送ライブラリー公開について」の封書が届きました。
これは、去年4月に放送されたYBSラジオスペシャル「水腫張満茶碗のかけら 地方病100年の闘い」が、この放送ライブラリーで保存され、公開することになったことから放送ライブラリーのチラシと共に丁重な依頼文書と承諾書が同封されていました。
山梨でも「水腫張満茶碗のかけら」と云うフレーズもすっかり聞かなくなり、若い方にはその意味も説明が必要になりました。
地方病が原因不明の奇病とされていた時代は、この病は「腹張り(はらっぱり)」とか「水腫張満(すいしゅちょうまん)」と呼ばれてきました。この病気に罹ると茶碗のかけらと同じで使い物にならない、あるいは治らないと云ったあきらめの意味や嘆きが込められた慣用句でした。
山梨放送の石川部長自らが取材したこの番組は、その後東日本グランプリ等に輝いたことは、石川氏からも報告があり知っていましたが、めでたく放送ライブラリー収蔵作品にも選定されたようです。
ローカル放送局の番組は、その地域内でしか視聴できませんから「水腫張満茶碗のかけら 地方病100年の闘い」も県内の限られた方しか聴いていないと思いますが、公開されれば横浜でいつでも聴くことが可能になりますので、出演者が言うのも無粋ですが「石川部長渾身の作品は一聴に値します」です。
2015年9月28日月曜日
杉浦醫院四方山話―444 『テアトル石和と映画・野火』
昭和町内には、イオンモールの中に県下最大のシネコンがあることは知っていますが、未だ行ったことはありません。5つ以上のスクリーンを備えた シネコンと言われる複合型映画館は、1990年代以降急速に増え、それに反比例するように「入れ替えなし・立ち見有り」の昔ながらの映画館は姿を消してしまいました。県内で、シネコンの対極として孤軍奮闘しているは、「テアトル石和」と「甲南劇場」「塩山シネマ」位でしょうか。
先日、石和在住の中学の同級生に「石和ならテアトル石和にはよく行くから・・」と話しましたら「やだー〇〇君、あんな映画観に行くの?」と、シネコン対極の場末映画館は、全て「甲南劇場」同様と思い込んでいるようでしたから「地元の名画館に足を運んでください」と丁重にお願いしましたが・・・・
そのテアトル石和で、原作 ・大岡昇平、塚本晋也監督の 「野火」を観てきました。「なぜ 大地を血で汚すのか 」のキャッチコピーで、塚本晋也監督が自ら主演して戦後70年を「野火」で問うた映画です。
薄汚れた館内(失礼)には、私を含めて20人そこそこの観客でしたが「何時になく多いなあ」が素直な実感でした。
まあ、私にとってこの映画館が落ち着くのは、スクリーンが舞台の奥にあることでしょう。
映画にハマって学生時代通った映画館には大小の差はあるものの必ず舞台と云うかロビーがあり、上演前に主演女優が現れて挨拶や実演のサービスに遭遇することもありましたから、無駄を配したスクリーンだけの映画館では落ち着きません。
大岡昇平氏の戦争体験3部作「野火」は、市川混監督作品で学生時代にも観ましたが、今回の塚本晋也監督作品は同じ原作とは思えない映像で、映画監督の視点や思想の違いについても考えさせられました。
もし大岡昇平氏がご存命でしたら大岡氏も塚本作品に軍配を上げていたことでしょう。
大岡氏同様、軍人として戦争に赴いた歴史学者・藤原彰氏の『餓死した英霊たち』にも「戦死者」の六割以上が「餓死(飢え死に)」だった事実が暴かれていますが、「英霊」が強制された「死」と極限の人間がどうなるのかをリアルに描き切った塚本作品は、戦争の加害性に重きを置いているのが 市川混監督作品との大きな違いになっていました。
東京まで行かずに石和でこの映画が観れたことを喜び、テアトル石和の末永い存続を期待してやみません。
2015年9月20日日曜日
杉浦醫院四方山話―443 『11/1 院内コンサート』
杉浦醫院の応接室にあるグランドピアノの詳細については、当190話・191話をご覧いただくとして、このピアノを活かしての院内コンサートを今年も開催します。今年は、杉浦家の親戚でもある音楽家お二人によるオータムコンサートです。
沼津市にお住いのテノールの杉浦誠氏は、熱海所記念病院の院長を勤める脳神経外科医ですが、年10回以上のステージをこなすオペラ歌手でもあります。
「ストレスの多い脳神経外科医にとって、オペラを歌うことがストレスを寄せ付けない最高のリラックスタイムにもなるので、今日まで二足のわらじを履いてきました」と笑いますが、メジャーな舞台なども多いプロでもあります。
純子さんも「誠さんは、声がきれいで歌がお上手でしたから、そちらの道に進むのかと思っていましたが、医者になったようですね」と幼少のころから目立った才能を発揮していたようです。
5年前に昭和町で行われた「杉浦家従兄弟会」に参加した折、当館ピアノの存在を知った誠氏が温めてきたコンサートが、ピアニスト・佐藤恵美さんとのスケジュールが合い今回開催できることになりました。
ピアニスト・佐藤恵美さんも杉浦誠氏の従兄弟ですから、純子さん姉妹もピアノを弾いていたように杉浦一族には音楽家や音楽趣味が共通しているように思います。
佐藤恵美さんは、国立音楽大学大学院を首席で卒業、成績優秀者に贈られるクロイツアー賞を受賞され、1992年には国際ロータリー財団奨学生として渡独し、ドイツ・デトモルト音楽大学・大学院過程を最優秀で終了したと云う経歴の持ち主です。
今回、ジャンルとしては固めのクラッシックですが、杉浦誠さんは「なるべく多くの皆さんが知っている親しみのある歌曲で構成しようと思います」とおっしゃっていましたから、オペラをマイクを通さず聴けるこの機会をお聴き逃しなくどうぞ。
院内ですから、定員やコンディションに限りや障害もありますが、昭和8年に杉浦家が山梨で一台だけ注文したと云う、皇太子(現天皇)生誕記念家庭用グランドピアノを使ってのコンサートですから悪しからずご了承ください。
参加申し込みは、電話275-1400(杉浦醫院)までどうぞ。
2015年9月17日木曜日
杉浦醫院四方山話―442 『絹彩画教室』
杉浦醫院2階の座学スペースを使っての伝統文化教室で、今回は「絹彩画入門教室」を開催しました。作業中心の教室ですからスペース的にも10人が限度でしたが、講師の三枝史博さんと作品が、山日新聞文化欄で大きく紹介されたこともあって、多くの方々から参加申し込みがありました。今回キャンセル待ちで参加できなかった方には、この場を借りてお詫び申し上げます。
三枝さんも挨拶の中で「絹彩画の歴史は新しく、どんな技法で出来るのかを知っていただき、愛好者を増やしたいと考え、体験教室を始めた」そうですから、11名の参加者全員が絹彩画は初体験でした。
今回は、三枝さんが用意した数点の図柄の中からトンボや鶴などの絹彩画に挑戦しました。
同じ図柄でも埋め込む絹布は自分の好みで選びますから、出来上がった作品は同じ図柄とは思えない多彩さで、これが絹彩画の特徴であり、面白さだと思いました。
参加者同士も初対面とは言え、油絵やアクリル画など日頃から絵画を描いて個展や公募展に出品をしているとか木目込み人形をやっているなど手を動かしながら和気あいあいと情報交換を楽しめたのもテーブルを囲んでの作業が、自然に打ち解けた会話につながったのでしょう。
椅子の生活に慣れた皆さんに3時間座っての集中作業は負担も多かったと思いますが、皆さんからは「これ一回でお終いですか?」「定期的にやりたいね」とか「今日の作品展を開きたい」と云った質問や要望も寄せられた有意義な教室でした。
2015年9月7日月曜日
杉浦醫院四方山話―441 『昭和まちしんぶん』
前話で紹介した甲府の古守病院の古守豊甫氏の孫・古守寛文さんは、医者である父・祖父に反抗した訳ではないでしょうが、違う道を歩む青年です。
その古守寛文さんが、昭和町に的を絞って、今年の4月にスタートさせたのが「プチコミ昭和まちしんぶん」で、既に9月号まで6号が町内各戸に配布されています。チラシのように新聞折り込みでは、手塩にかけて創る新聞が読まれず、ゴミ箱に直送されるのでは?と、一軒一軒手配りで届けていることにも古守さんの意気込みを感じます。
甲府市在住の古守さんが「なぜ昭和町しんぶんなの?」を聞いたところ「現在の力量からすると昭和町がジャストサイズ」とのことですから、古守さんが代表取締役の株式会社アグストの成長次第では、もっと拡がる可能性もあるのでしょう。
A4版8ページのしんぶんの購読料は無料ですから、取材制作費やポスティングまでの経費は広告収入でしょう。紙面が読まれ、広告効果が上がれば問題ありませんが、広告主が定着するまでは営業も大きな位置を占めていることでしょう。
一面には、昭和町内でご活躍の方に古守さんが直接インタビューした記事が定着しています。
これには創刊号で角野町長が「住みよいまち 昭和町へようこそ!」と笑顔で応じたことが大きかったように思います。町の広報とは違った視点から昭和町を紹介して愛着をもってもらおうと云う古守さんの姿勢が覗えます。
こう云ったミニコミ誌が育つ町には自然と人が足を運びますから、県内唯一の地域限定民間しんぶんが継続発行されるよう、杉浦醫院の話題を提供することから広告の店に行ってみるまで、私も自分の出来る水やりで、「昭和まちしんぶん」を育てていきたいと思います。
2015年9月2日水曜日
杉浦醫院四方山話―440 『長寿村・棡原(ゆずりはら)』
山梨県上野原市にある棡原地区は、日本の長寿村として有名ですが、近頃あまり話題になりませんね。
話題と云えば、「カスピ海ヨーグルト」も消えましたね。
これは世界の長寿国として有名なカスピ海に面し、5000メートル級の山々に囲まれたコーカサス地方の人々が、毎日飲んでいる長寿食と云うことでブームになったヨーグルトでした。
コーカサス地方の人々の健康を支えてきた発酵食「ケフィア」は、カスピ海ヨーグルトとは若干違い、飲み物と云うより食べ物のようですが、「ケフィア」より「カスピ海ヨーグルト」の方がイメージ的に日本人受けしてのブームだったのでしょう。
フィリピンの日本住血吸虫症患者を救う活動を長年続けてこられた元市立甲府病院の林正高先生から、棡原地区の長寿者の医学的調査をまとめた「上野原棡原地区の高齢者の中枢神経系の健康度について」の論文4巻と「長寿・山梨県上野原町棡原地区老人の健やかさについて」の論文コピーをご寄贈いただきました。
「長寿村・棡原」と聞けば「古守先生」と云うように棡原を日本の長寿村として世に知らしめたのは、古守病院の古守豊甫医師で、昭和43年以降、古守豊甫氏を班長に「長寿村棡原総合研究班」が毎年棡原で老人巡回検診を行い、長寿の背景は「棡原の食文化」にあることを紹介してきました。
前述の「上野原棡原地区の高齢者の中枢神経系の健康度について」の論文4巻は、林正高先生と古守病院の古守豊甫・古守泰典・古守豊典の3医師及び棡原診療所の古守知典医師による連名論文で、林先生も「長寿村棡原総合研究班」で共に巡回検診を行い、林先生の専門である中枢神経系の健康度を脳波測定と長谷川式痴呆スコアで調査した結果です。
この論文でも棡原地区独特の食生活であるアワ、ヒエ、ソバ、ムギ等の雑穀を中心とした穀菜食が長寿に繋がっていることを再確認すると共にコーカサス地方同様、傾斜地での労働や生活が平地に比し筋紡錐の使用が多く、動脈硬化予防に大きな役割を担っているなど地理的要因も挙げていますが、林先生は「更には古い日本の家族力動が老人に使命感も抱かせることの精神面も一大要因」と指摘しています。
肉食など欧米化した食生活や自動車や農機具の普及、核家族化の進行などは長寿村・棡原にも及び、平均的な寿命になり近頃あまり話題にならなくなったのでしょう。
「健康年齢」とか「健康寿命」などという新たな概念も強調されるご時世、林先生ご指摘の「老人に使命感も抱かせる精神的要因」は、上野千鶴子センセイ云う所の「きょうよう(今日用がある)」「きょういく(今日行く所がある)」と重なりますから、何時の時代も「気持ちだよ 気持ちだよ」の吉田拓郎だということでしょう。
登録:
投稿 (Atom)